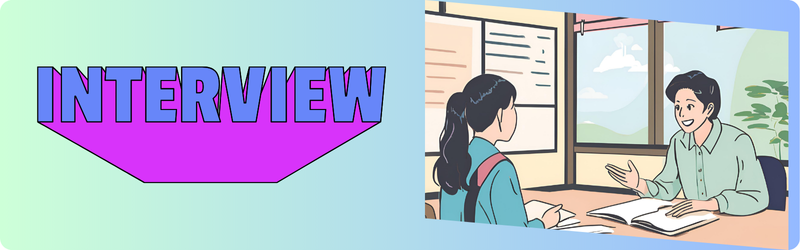
今回は公募型推薦で大学へ進学した卒業生の方に,公募型推薦の入試についてのインタビューにご協力いただきました。
ここでは,インタビューの内容を記事にして紹介させていただきます。
(進路指導課)
Q1卒業した年度や今の状況を教えてください。
A12023年度の3月(2024年3月)に旭陵高校を卒業して、今年から大学1年生になりました。
Q2大学に合格したときの入試の形態を教えてもらっていいですか?
A2私が受験した入試形態は、公募制推薦の教科型という方式です。公募制推薦の教科型は,教科の学力試験(国数英から2教科選択)と面接の点数、調査書の合計で合否が判定される方式でした。学力試験では、数学と英語を選んで受験しました。
Q3今在籍されている大学は第一志望でしたか?
A3はい、専願の推薦入試が第一志望でした。
教員コメント
一般的に専願の方が,併願よりも合格しやすい傾向にあるので,第一志望であれば専願がおすすめです。
一般的に専願の方が,併願よりも合格しやすい傾向にあるので,第一志望であれば専願がおすすめです。
Q4その大学を受験しようと決めた時期はいつでしたか?
A4決めたのは4年生(最終学年)になったタイミングだったので、2023年の4月頃だったと思います。
Q5大学の決め手は何でしたか?
A5志望していた学部がある大学が限られていたので、3年生の時から当時の担任の先生とお話をし、学部について調べ、「自宅から通えて穏やかな校風であること」を条件にして決めました。
教員コメント
志望校を考える過程では,ぜひ我々教員にもご相談していただければと思います。もちろん保護者の方にも。
志望校を考える過程では,ぜひ我々教員にもご相談していただければと思います。もちろん保護者の方にも。
Q6オープンキャンパスには行かれましたか?
A6はい、8月のオープンキャンパスに参加しました。その際に学生さんにキャンパス案内をしていただき、環境の心地よさを実感しました。そのことがずっと心に残っていて、受験をする最終的な決め手になったと思います。
教員コメント
オープンキャンパスは,学校や先生,学生さんの雰囲気が知れ,直接話を聞ける貴重な機会なので,興味のある学校のオープンキャンパスには,積極的に参加してみてください。
オープンキャンパスは,学校や先生,学生さんの雰囲気が知れ,直接話を聞ける貴重な機会なので,興味のある学校のオープンキャンパスには,積極的に参加してみてください。
Q7第一志望の大学を決め,その後どのような入試を受験しようと思っていましたか?
A7初めは一般入試を考えて受験勉強を4年生(最終学年)の4月から始めました。ですが、ちょうど2024年度入試から公募制推薦が始まるとのことだったので、チャレンジしてみようかなと思い、公募制推薦入試対策を優先し準備をしていきました。
Q8一般受験では,第一志望の大学以外にもいくつか受けるということを想定していたと思うんですけれども、公募で複数受けようということは考えていましたか?
A8それは考えていませんでした。専願の公募制推薦が第一志望というのもあったので、他の公募制推薦は検討せずに、第一志望のみを受けました。もし落ちた時の進学先は、一般入試で確保しようと考えていました。
教員コメント
一般入試の対策と並行して,推薦入試の対策を同時に行うことは時間的・労力的・精神的に負担の大きいことです。推薦入試で受験する学校の数は1校もしくは,少数に絞ることをおすすめします。
一般入試の対策と並行して,推薦入試の対策を同時に行うことは時間的・労力的・精神的に負担の大きいことです。推薦入試で受験する学校の数は1校もしくは,少数に絞ることをおすすめします。
Q9公募制推薦を受けようと決めた時期はいつ頃でした?
A9決めた時期は、5月ぐらいだったと思います。大学の入試情報が開示されたタイミングで、すぐに公募制推薦の受験を決めました。
Q10公募制推薦対策の準備はいつ頃からどんなことをしてました?
A10まず5月頃に公募制推薦で入試を受けることを決め、一番初めに担任の先生に相談をしに行きました。自分では何をするべきかわからなかったので、推薦がもらえるのか、推薦をもらうためにはどうしたらいいのかという説明をしていただき、入試の面接に合わせた準備と学力試験のための勉強を徐々に始めました。
教員コメント
まずは担任に相談し,志望理由書の作成や面接対策を担任や進路の教員と進めていきましょう。推薦入試対策の講座を提供している予備校もありますので,予備校も活用して対策を進めることも可能です。
まずは担任に相談し,志望理由書の作成や面接対策を担任や進路の教員と進めていきましょう。推薦入試対策の講座を提供している予備校もありますので,予備校も活用して対策を進めることも可能です。
Q11初めに学力試験の対策はどのように行っていましたか?
A114月から予備校に入ったこともあり、自然と勉強をする環境が整ったところにいました。自宅では学校のレポートに加えて、予備校でもらったテキストを解いたり、予備校に行っている間は予習復習をやったりしていました。入試の出題範囲がかなり限られていたので、基礎を固めつつ過去問を使って似た傾向の問題をひたすら解いていました。
Q12予備校は週何日くらい通われていましたか?
A12週5日通っていました。大学に入ってからも週5日通うことを想定して、予行練習というような感覚でした。
Q13次に面接の対策はどのように行っていましたか?
A13面接の対策は主に学校と予備校で行っていました。学校では、自宅で考えた志望理由書の文面を元に日曜日のスクーリングの後に担任の先生と添削し、面接の練習をしました。6月ごろから志望理由書の作成を始め、8月ごろからは志望理由書の作成と並行して、面接形式の練習を月に1回のペースでしていました。
予備校では小論文の担当の先生がいらっしゃったので、その先生に自分が書いた志望理由書を添削していただいたり、クラス担当の先生に面接形式で練習をしてもらうことを月に2,3回していました。それも6月頃から徐々に行っていったという感じです。
Q14志望理由書を作成する際に苦労したこととか大変だったことはありましたか?
A14志望理由書を考えることにはかなり苦戦しました。自分の考えや気持ちがなかなか言葉にできなくて、伝えたいのに伝わらないもやもやがずっとあったのを覚えています。
(そのもやもやをどのように形にしていきましたか?)
今振り返ると、もやもやを形にできたのは大きく分けて2つのことがあると思っています。1つは担任の先生との面談の際に、自分が考えや気持ちを文章でなく、短い言葉でとにかく話したことです。拙い単語の羅列だったと思うんですけど、先生にたくさん質問していただいたことでたくさんアウトプットすることができ、少しずつ形になっていきました。
もう1つは本を読むのが好きなので,その中で自分が伝えたい気持ちに近い文章から、言葉を借りたことです。少し背伸びをしたやり方でしたが、自分の感情に近い言葉を見つけやすくて、少しずつまとまっていったという感じです。
個人的には、頭の中で「どうしよう」と悩むのではなく、会話を通して言葉で相手に伝えたことがモヤモヤを解消できたきっかけだったと感じています。
教員コメント
志望理由書には,自分の経験や強みに基づいた志望動機を考える必要があります。自分の経験や強みは,誰かに話すことで自覚できたり,言語化できたりすることもあるので,ぜひ担任や進路の教員(話がしやすい教員にお願いするのも◎),保護者の方や友人など,周りの方にも相談しながら考えてみてください。
志望理由書には,自分の経験や強みに基づいた志望動機を考える必要があります。自分の経験や強みは,誰かに話すことで自覚できたり,言語化できたりすることもあるので,ぜひ担任や進路の教員(話がしやすい教員にお願いするのも◎),保護者の方や友人など,周りの方にも相談しながら考えてみてください。
Q15志望理由書は予備校の先生や担任の先生以外の人に見てもらうことはありましたか?
A15はい。私はよく家族に見てもらっていていました。一番身近な存在なので、「私らしさ」をよくわかっているんです。ある程度構成が固まった志望理由書を一度家で読み上げて、「それ本当に思ってる?」「ちょっとそれはあなたの言葉じゃないんじゃない?」とはっきり伝えてもらうことを何度も繰り返しました。私にしか書けない文章を書くための参考になって、自分らしさを追求できたかなと思います。
教員コメント
受験にかかる費用や学費を保護者の方に出していただく方も多いと思います。ぜひ保護者の方には相談をして,自分の考えや思いを理解してもらいながら,受験に臨んでいけるといいですね。
受験にかかる費用や学費を保護者の方に出していただく方も多いと思います。ぜひ保護者の方には相談をして,自分の考えや思いを理解してもらいながら,受験に臨んでいけるといいですね。
Q16予備校の先生,担任の先生,ご両親と色んな人に話を聞くと,みんなバラバラなことを言う可能性もあると思いますが,自分の中で上手く整理できないことがありましたか?
A16そうですね、実際よく予備校の先生に「あまりいろんな人に頼みすぎない方がいいよ」と言われていました。でも、私の中では正解がわからない不安が一番大きかったので、いろんな人に話して返ってくる答えから自分が伝えたいものを探していました。たくさんの人にお願いすることは、私にとっては、志望理由書を完成させることよりも不安を解消するための1つの手段だったのかなと思います。
Q17最初に志望理由書を考えるときに苦労したと思うんですが,その後の面接の練習をする際に志望理由書で考えたことは活きましたか?
A17はい、面接練習の中で志望理由書で考えたことにはかなり助けられました。面接練習では、先生にたくさん質問をしていただく中で、準備していないものがたくさんありました。その際、志望理由書を制作する際に考えたことを思い出してアドリブで答えることに繋げることができました。
また入試当日、面接をするときにも面接官の先生の手元に志望理由書が置いてありました。入試の中でも特に面接は緊張したのですが、志望理由書を作成する中で自分のやりたいことや目的を一貫して考えられていたので、どんな質問が来ても大丈夫だと思えました。志望理由書が揺るがない自分の軸のようなものになっていたと思います。
教員コメント
志望理由書をしっかりと考えることが,その後の面接や小論文の対策にもつながります。ここはぜひ力を入れて取り組んでみてください。
志望理由書をしっかりと考えることが,その後の面接や小論文の対策にもつながります。ここはぜひ力を入れて取り組んでみてください。
Q18面接の対策で,基本的な質問(志望理由,高校時代に頑張ったこと,入学してからやりたいこと,卒業後にやりたいことなど)以外に考えたことってありましたか?
A18自分についての質問に答えられるように準備をしました。例えば、趣味・特技、学部に関連することで今知っている知識、日常生活に関わることです。何気ない質問も聞かれる想定でいたので、いろいろなことに目を向けて日常を振り返って準備をしました。
Q19当日入試を受けるときの気持ち(自信や不安)はどうでしたか?
A19前日の夜からお腹が痛くて、大丈夫かなとずっと不安でした。自分が試験を受けているところが想像できなくて、そわそわしたり、緊張で手が震えたりしていました。
当日も緊張しすぎて、送ってもらった車から降りられなかったり、開始時間ギリギリまでトイレで1人で過ごしたりしていました。特に面接では、入退室の時にお辞儀をすると思うんですけど、その時もオイルを足さないといけないくらいぎこちなくなってしまいました。
Q20実際に面接が始まってからはどうでした?
A20面接が始まった最初は何を質問されるかわからないのでずっと震えていました。ですが、面接官の先生がオープンキャンパスの際にお話をしたことがある先生で、すぐにリラックスすることができました。見たことのある先生だ!と気づいてからは、練習の通り、穏やかな気持ちで話すことができたなと思います。先生方が思っていたよりも穏やかな表情で聞いてくださったので、落ち着いて臨めました。
教員コメント
しっかり対策されていても,当日は緊張すると思います。可能な限り準備をしっかりとして,自信を持って望めるといいですよね。また,オープンキャンパスに参加して,顔を知っている先生がいることが安心感につながることもあるんですね。
しっかり対策されていても,当日は緊張すると思います。可能な限り準備をしっかりとして,自信を持って望めるといいですよね。また,オープンキャンパスに参加して,顔を知っている先生がいることが安心感につながることもあるんですね。
Q21実際にされた質問の内容はどのようなものでしたか?
A211番初めに入学してから頑張りたいことを聞かれました。その後に楽しみにしている授業や大学卒業後の進路、どのような大人になりたいのかについて聞かれました。私の場合、面接の持ち時間が少し余ってしまったので、趣味・特技についても聞かれました。高校で頑張ったことなど過去のことより、将来のことについてよく聞かれたという感じです。
Q22面接の時間や面接官の人数はどうでしたか?
A221人持ち時間が8分と決まっていました。また、受験生1人に対し、面接官の先生が2人でした。
Q23受験が終わって,合格発表まで時間が空いたと思うんですが,それまでの期間はどう過ごしてましたか?
A23入試から合否発表までの2週間はとにかく不安でした。緊張のしすぎで入試の手応えがあったのか、なかったのかも覚えていなくて余計に落ち着きませんでした。少しでも勉強のことを考えると、「大丈夫かな」と不安になってしまうので校外学習に参加したり、少し遠出をしたりして気を紛らわしていました。合格発表までの期間は勉強する時間は学校のスクーリングの時だけにして、その時期はあまり一般入試に向けた学力試験の勉強も手につかなかったです。
Q24今回無事に合格できたのでよかったんですけど,仮に合格できなかった場合はどうやって気持ちを切り替えて一般入試まで頑張ろうとか考えてました?
A24そうですね、私の場合は、公募制推薦の時点で1校しか受けていなかったので、落ちてしまったらどの大学にも行けない状況でした。なので大学に行きたい、やるしかないと奮い立たせて気持ちを切り替えていたと思います。
Q25合格が決まってから大学に入学するまでの間に課題はありましたか?
A25大学からは課題はなかったのですが、学部の方から推奨のテキストリストが送られたのでそれを自分でやっていました。私が通っている学部は文理を問わない学問なのですが、どちらかというと理系の授業が多くなるので、化学や生物のテキストを使って復習を進めていました。
Q26受験を振り返ってあの時こういうことやっておいたのが良かったなとか,逆にもっとこうしとけば良かったのになと思うことはありますか?
A26そうですね。まずやって良かったなっていうのは、早い段階で先生方に相談ができたことだと思います。自分が何をしていいのかどういう将来を描いていくのかが何も想像がつかなかったので、先生方と継続的にお話しをして少しずつ解像度を高めていけたのは良かったなと思っています。
逆にやった方が良かったなっていうのは、不安を取り除くためにいろいろな可能性をイメージすることです。受験会場は旭陵高校でのテストの時より、ずっと大きくて、たくさんの人がいました。全く想像をしていない環境だったので、より緊張してしまったと思います。元々、私はとても不安になりがちなので、どんな環境でも大丈夫だと思えるようにいろいろな可能性を想定していれば、合否が出るまでの2週間ももう少し穏やかに過ごせたんじゃないかなと思います。
Q26最後の質問なんですけど、旭陵高校にもこういう公募制やAOのような年内入試で大学を受験したいと思っている在校生の方に,何かアドバイスやメッセージがあればお願いします
A26旭陵高校は基本的にそれぞれが一人で過ごしていると思うんですけど,受験は一人で受けるものではないと思うので,先生方であったり,クラスの子とか、誰かと話して自分の将来の解像度を少しずつ高めていくといいと思います。大学に進学した今振り返って、改めて通信制高校を卒業することの大変さに気づきました。最終学年まで進み、たくさんの人が悩む中で、自ら進路を決めたことがすでに誰にも負けない強みだと思います。今の自分を誇りに思って、自分のペースで頑張ってください!応援しています!
インタビューへのご協力ありがとうございました!(2024年10月 進路指導課 加藤)
※画像は生成AIを利用して作成しました。

一般入試の受験も検討されている方は,面接や小論文だけでなく学力試験もセットの入試形態を選択することもおすすめです。